全身のツボは世界保健機関が定めたもので361個あります。
これが左右対称にあるものが多く、さらに定められていない「奇穴」も含めると約700個のツボが全身にあります。
もちろん、国家試験を受けるためにすべてを覚えていました。(過去形!?笑)
今でもそんなツボ聞いたことないわ、ってのはありませんが、
一度も使ったことがない(使える場所にないものも)ってのはいくつかあったり、
久しぶりに使うわ、ってのもありますねぇ、でもこれは私だけではないはず!?
ツボの名前って難しい漢字だったり、常用漢字ではないものも多く、おもしろい名前のものがたくさんあるんです。
その中の少しをご紹介。
その名前、どうしてそうなった?みたいものから、詩的なものまで。
でもこれ、ただのオシャレなネーミングではなく、
それぞれにちゃんとした“意味”と“イメージ”があるんです。
風池(ふうち)〜風がたまる池〜
首の後ろ、髪の生え際のくぼみにあるツボ。
肩こり、頭痛、目の疲れなどに使われます。
名前の「風池」は、“風が溜まる池”という意味。
昔の人は、首筋を風が通る道のように感じていたんです。
風邪(ふうじゃ)という言葉もあるように、風は「邪気」を運ぶとされていました。
つまりここは、外から入ってくる風邪(かぜ)を防ぐ関所のような場所。
現代で言えば、「首元を冷やすな!」というおばあちゃんの知恵そのものです。
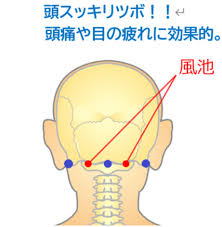
百会(ひゃくえ)〜百の気が会する場所〜
頭のてっぺんにあるツボ。自律神経のバランスや不眠、めまいなどに用いられます。
「百会」とは、“全身の気が百(たくさん)集まるところ”という意味。
イメージとしては、体のエネルギーが頭の頂点に集まり、天に通じるポイント。
気が滞ると心も体も重くなる。だから百会を刺激すると、
「なんだかスーッとする」「頭が軽くなる」という感覚が生まれるのです。
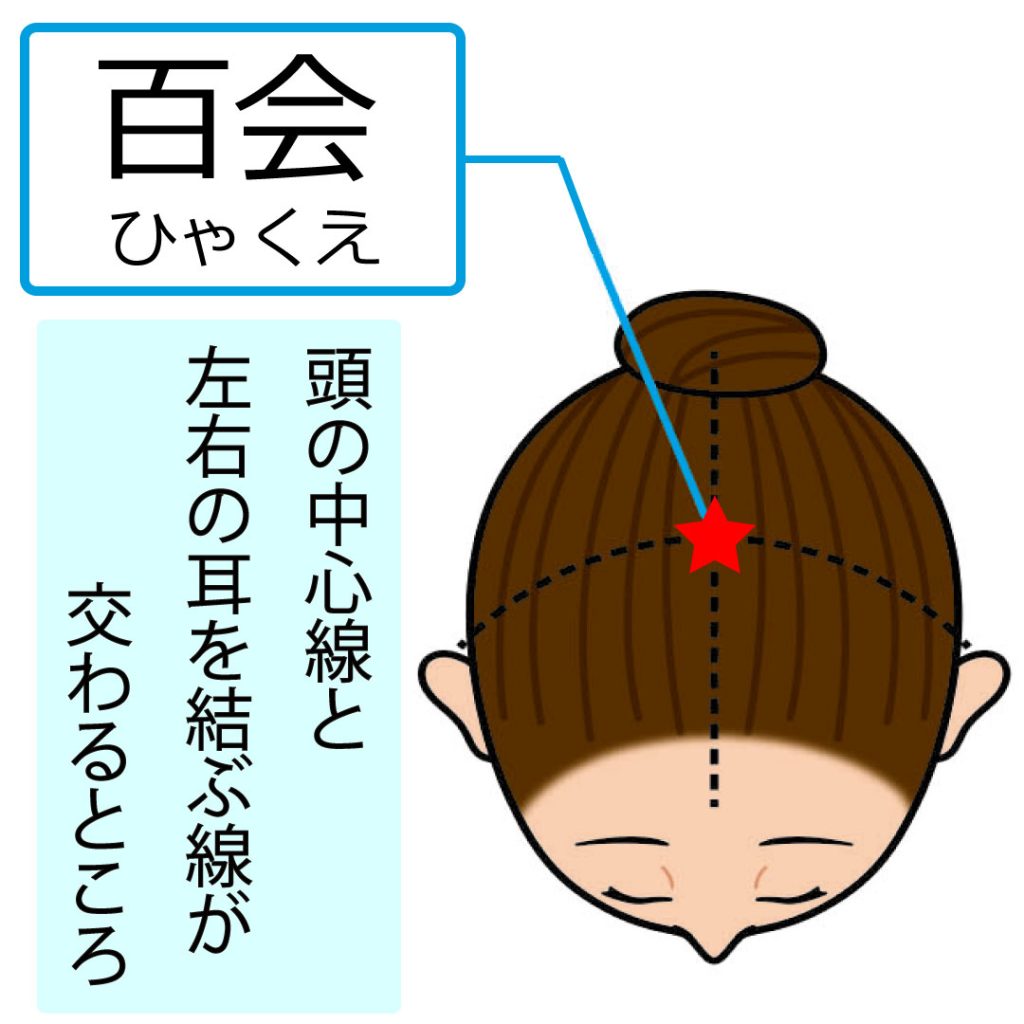
太衝(たいしょう)〜大きく流れ出る勢い〜
足の甲、親指と人差し指の間にあるツボ。肝の経絡に属します。
「太」は“大きな”、“衝”は“勢い”を意味します。
気が勢いよく流れ出す場所=“気の滞りをほどくツボ”。
イライラやストレスが溜まった時に押すと、まさに“怒りの出口”を開くような感覚があります。
実際、太衝は“肝の気うっ滞”を流す代表ツボ。
「怒りっぽくなったら太衝を押せ」と昔から言われています。

名前が詩的なツボたち
・天柱(てんちゅう)…天を支える柱。首すじの力強いツボ。
・神門(しんもん)…心(しん)の門。心を鎮めるツボ。
・三陰交(さんいんこう)…三つの陰の経絡が交わる、女性の要のツボ。
ツボの名前には、古代人の感性と観察力がぎゅっと詰まっています。
ツボの名前は「身体の風景」。
それを知ることで、自分の体との対話が少し深まるような気がします。
西洋医学って素晴らしい、って思いますし、お世話にもなっていますが、東洋医学も面白いんですよ~。
